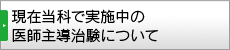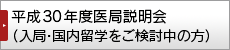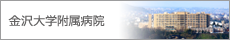教室について
矢野教授の研究との出会い
研究の周辺から
転移研究と分子標的治療に魅せられて
金沢大学がん研究所腫瘍内科研究分野
矢野聖二
研究者としてのスタート
「転移を制するものはがんを制す」。使い古されたフレーズではあるが、人類の永遠のテーマかもしれない。私が、研究をはじめたのは1991年、徳島大学内科学第三講座の大学院に入学した春である。内科医としてスタートしたばかりであったが、当時の医局長であった曽根三郎先生(現徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部分子制御内科教授)のお誘いがあり研究の道に足を踏み入れた。当時の研究室は、末梢血から単離した単球を種々の物質で刺激して、TNFやIL-1に感受性のあるメラノーマ細胞A375をどれだけ殺すことができるかなど、がん免疫に関するin vitroでの実験を中心にやっていたと記憶している。多剤耐性癌細胞が発現するP糖蛋白質に対する抗体(MRK16)を鶴尾隆先生(当時東京大学分子細胞生物学研究所所長、現癌研究会癌化学療法センター所長)からいただき、単球が多剤耐性癌細胞に対し誘導するMRK16のADCC(抗体依存性細胞傷害反応)を、免疫抑制剤であるシクロスポリンAが増強するということを見出して、こじんまりと学位をいただいた。
転移研究との出会い
その後、MRK16によるADCCの効果をin vivoで確認したいという強い思いがあり、それを検証できるモデルの作製を試みた。その辺りにおいてあった学会の抄録集を開いてみると、肺癌細胞株H69をSCIDマウスに静注すれば肺転移ができると書いてあった。今思い起こすと、その抄録集は私のなかで最も思い入れの強い学会である日本がん転移学会(当時日本がん転移研究会)のものであった(笑)。書いてあるとおりやってみたが、肺転移など全くできなかった。これが私の転移研究の第1歩であった。当時、「がんに対する生体防御機構で一番働いていそうなのはNK細胞」という知識はあった。そこで、NK細胞を除去できるasialoGM1抗体を勝手に購入してSCIDマウスに打ってみた。そうすると、なんと肝臓やリンパ節に転移ができた。肺転移ができないという予想外の結果ではあったが、とにかくMRK16の効果を試すことのできるモデルができて論文が書けそう。ということで、教授に就任したばかりの曽根先生に報告した。すると、「これはいい車(モデル)ができたね。これでどこにでも乗っていけるよ(いろんな実験ができるよ)。今後大々的に展開して行こう!」と予想以上にpositiveな言葉をいただいた。その後、曽根教授が大阪大学の宮坂昌之教授と田中稔之先生(現兵庫医療大学教授)より「効率よくNK細胞を除去できる抗体(TM-1:抗マウスIL-2受容体鎖抗体)」を供与していただき、より再現性の高いヒト肺癌細胞の多臓器転移モデルができたわけである。
そうこうしているうちに、曽根教授の留学先のボスであるIsaiah J Fidler教授が、かの「日本がん転移研究会」に出席する直前に徳島を訪問した。1996年のことだったと記憶している。つたない英語で自分のデータを紹介したが、上記の転移モデルは「wonderful」と(社交辞令だったかもしれないが)ほめてもらった。彼は植物が大好きでランの人工栽培をしている工場の見学に行ったが、私はどきどきしながら案内役を勤めた(写真1)。その翌日Fidler教授から、「おまえには給料を払ってやろう、いつからうちのラボに来るのか?」と聞かれた。全く留学など考えていなかったところに突然聞かれたので絶句したのを覚えている。内科医として一人前でもないのに留学などして臨床を離れ、今後医者としてやっていけるのか?アメリカに家族を連れていってまともに生活できるのか?Fidler教授が転移の大御所という以外彼のラボのことを全く知らなかった私は正直非常に迷った。数日後、日本がん転移学会の懇親会で、Fidler教授のラボに留学された北台靖彦先生(広島大学消化器内科)に「Fidlerラボへの留学生は今20人待ちですよ。それに留学は日本で疲れた心のリハビリと思えばいいじゃないですか!」と言われ、それもそうかと思った。転移研究をはじめたばかりだが、どうせなら大御所のところで鍛えてもらうのもいいかと決心して曽根教授に留学のお願いに行った。二つ返事でOKをもらい、とんとん拍子に事が運んで、1997年秋にテキサス州はヒューストンに留学した。ヒューストンではそれこそ様々な経験をさせてもらった。脳転移や血管新生など、自分にとっては真新しい分野の研究をさせてもらい、転移を形成するがん細胞の巧妙な手口に感心するとともに転移研究の奥深さを実感した。マウスの内頚動脈にがん細胞を注入する顕微鏡手術を約1ヶ月かけて習得し、はじめて脳転移させることに成功した日のことは今でも忘れられない。Fidler教授から「天才!」とおだてられ「木に登ってしまった」かもしれない。さらに、毎週月曜日のFidlerラボセミナーでは、まるで大統領の演説のようなFidler教授の名講義をきいた。「また同じ話だ、、、。」と思うこともあったが、ターンオーバーの早いラボのスタッフに共通の基礎知識を植え付けるには重要なことだったのだと思う。いろんな国から来た研究者の気質も理解できた。自分の視野を広げる意味でも、やはり留学は貴重な経験になったと思う。家族も「全く込み合っていないディスニーワールドを待ち時間ゼロで楽しんだこと」を最良の思い出としているようだ。
分子標的治療との出会い
2年が経過し1999年秋に帰国した。呼吸器内科医として臨床の現場に復帰。丁度1年が経過したところでイレッサの臨床第2相試験(IDEAL-1)に参加する機会に恵まれた。FidlerラボでEGFR-TKIの実験も行ったが、ヒト肺腺がん株PC14の肺転移モデルでは全く効かなかったので、「こんな薬、効くはずない」と内心思っていた。ところが、徳島大学から3例目としてエントリーした私の患者さんが著効した。「是非このかたにはイレッサの治療を試して欲しい」との曽根教授の意向があり、私も患者さんにお勧めした。患者さんはあまり乗り気ではなかったが「先生がそこまで言うんだったら、飲んであげてもいいわよ」と同意された。治療開始1週間後、「増悪しているのではないか?」と心配で、撮影された胸部X線フィルム(当時はまだフイルムであった)を放射線部まで自分で取りに行ったが、信じられないくらい腫瘍が縮小していた。我が目を疑った。患者間違いではないかと名前を確認したが、間違っていなかった。その患者さんは、今では常識であるが(当時はもちろんわかっていなかった)EGFR-TKIが奏効する因子「女性、腺癌、非喫煙者の日本人」をすべて満たしていた。病室まで走っていって患者さんにフィルムをみせると、患者さんは涙を流しながら何度もおじぎして感謝してくれた。私は、「よかったね」と右手を差し出し握手をした。それから、その患者さんと私の間では「握手」が幸運を期待するときのおまじないになった。これが私の分子標的薬との出会いで、あまりにも印象的な出来事であった。
やっぱり研究はすばらしい
以後、ヒト肺癌細胞の多臓器転移モデルを用いて転移機構の解析や新規分子標的の探索を、臨床的にも分子標的薬のバイオマーカーの探索研究を行っている。2007年4月より金沢大学がん研究所腫瘍内科研究分野に異動する機会を与えられ、新天地でも「転移に対する分子標的治療の基礎および臨床研究」をライフワークに掲げやって行きたいと考えている。その原動力となっているのは、「転移モデルができたときの感動」であり「分子標的治療が効いて患者さんと共有した感動」だと思う。このような感動を味わうことができたのは、「大学院生の思いつき」研究を寛大な心で許容し先見的な視点に立って発展させてくれたボスや、困ったときに相談に乗り助けてくれた先輩、同僚、後輩のおかげと心から感謝している。最近、研究をする若い人が減ったと嘆かれているが、こんなにもおもしろくて、かつ感動を味わうことのできる研究をやらないのは損!研究の魅力を若い人たちに伝えて活性化するとともに、自由な発想を生かした研究ができる環境を提供できるよう努力して行きたいと思っている。そして、「転移を制する」ことで若い研究者や患者さんとより多くの感動を味わい共有できることを願っている。
転移研究と分子標的治療に魅せられて
金沢大学がん研究所腫瘍内科研究分野
矢野聖二
研究者としてのスタート
「転移を制するものはがんを制す」。使い古されたフレーズではあるが、人類の永遠のテーマかもしれない。私が、研究をはじめたのは1991年、徳島大学内科学第三講座の大学院に入学した春である。内科医としてスタートしたばかりであったが、当時の医局長であった曽根三郎先生(現徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部分子制御内科教授)のお誘いがあり研究の道に足を踏み入れた。当時の研究室は、末梢血から単離した単球を種々の物質で刺激して、TNFやIL-1に感受性のあるメラノーマ細胞A375をどれだけ殺すことができるかなど、がん免疫に関するin vitroでの実験を中心にやっていたと記憶している。多剤耐性癌細胞が発現するP糖蛋白質に対する抗体(MRK16)を鶴尾隆先生(当時東京大学分子細胞生物学研究所所長、現癌研究会癌化学療法センター所長)からいただき、単球が多剤耐性癌細胞に対し誘導するMRK16のADCC(抗体依存性細胞傷害反応)を、免疫抑制剤であるシクロスポリンAが増強するということを見出して、こじんまりと学位をいただいた。
転移研究との出会い
その後、MRK16によるADCCの効果をin vivoで確認したいという強い思いがあり、それを検証できるモデルの作製を試みた。その辺りにおいてあった学会の抄録集を開いてみると、肺癌細胞株H69をSCIDマウスに静注すれば肺転移ができると書いてあった。今思い起こすと、その抄録集は私のなかで最も思い入れの強い学会である日本がん転移学会(当時日本がん転移研究会)のものであった(笑)。書いてあるとおりやってみたが、肺転移など全くできなかった。これが私の転移研究の第1歩であった。当時、「がんに対する生体防御機構で一番働いていそうなのはNK細胞」という知識はあった。そこで、NK細胞を除去できるasialoGM1抗体を勝手に購入してSCIDマウスに打ってみた。そうすると、なんと肝臓やリンパ節に転移ができた。肺転移ができないという予想外の結果ではあったが、とにかくMRK16の効果を試すことのできるモデルができて論文が書けそう。ということで、教授に就任したばかりの曽根先生に報告した。すると、「これはいい車(モデル)ができたね。これでどこにでも乗っていけるよ(いろんな実験ができるよ)。今後大々的に展開して行こう!」と予想以上にpositiveな言葉をいただいた。その後、曽根教授が大阪大学の宮坂昌之教授と田中稔之先生(現兵庫医療大学教授)より「効率よくNK細胞を除去できる抗体(TM-1:抗マウスIL-2受容体鎖抗体)」を供与していただき、より再現性の高いヒト肺癌細胞の多臓器転移モデルができたわけである。
そうこうしているうちに、曽根教授の留学先のボスであるIsaiah J Fidler教授が、かの「日本がん転移研究会」に出席する直前に徳島を訪問した。1996年のことだったと記憶している。つたない英語で自分のデータを紹介したが、上記の転移モデルは「wonderful」と(社交辞令だったかもしれないが)ほめてもらった。彼は植物が大好きでランの人工栽培をしている工場の見学に行ったが、私はどきどきしながら案内役を勤めた(写真1)。その翌日Fidler教授から、「おまえには給料を払ってやろう、いつからうちのラボに来るのか?」と聞かれた。全く留学など考えていなかったところに突然聞かれたので絶句したのを覚えている。内科医として一人前でもないのに留学などして臨床を離れ、今後医者としてやっていけるのか?アメリカに家族を連れていってまともに生活できるのか?Fidler教授が転移の大御所という以外彼のラボのことを全く知らなかった私は正直非常に迷った。数日後、日本がん転移学会の懇親会で、Fidler教授のラボに留学された北台靖彦先生(広島大学消化器内科)に「Fidlerラボへの留学生は今20人待ちですよ。それに留学は日本で疲れた心のリハビリと思えばいいじゃないですか!」と言われ、それもそうかと思った。転移研究をはじめたばかりだが、どうせなら大御所のところで鍛えてもらうのもいいかと決心して曽根教授に留学のお願いに行った。二つ返事でOKをもらい、とんとん拍子に事が運んで、1997年秋にテキサス州はヒューストンに留学した。ヒューストンではそれこそ様々な経験をさせてもらった。脳転移や血管新生など、自分にとっては真新しい分野の研究をさせてもらい、転移を形成するがん細胞の巧妙な手口に感心するとともに転移研究の奥深さを実感した。マウスの内頚動脈にがん細胞を注入する顕微鏡手術を約1ヶ月かけて習得し、はじめて脳転移させることに成功した日のことは今でも忘れられない。Fidler教授から「天才!」とおだてられ「木に登ってしまった」かもしれない。さらに、毎週月曜日のFidlerラボセミナーでは、まるで大統領の演説のようなFidler教授の名講義をきいた。「また同じ話だ、、、。」と思うこともあったが、ターンオーバーの早いラボのスタッフに共通の基礎知識を植え付けるには重要なことだったのだと思う。いろんな国から来た研究者の気質も理解できた。自分の視野を広げる意味でも、やはり留学は貴重な経験になったと思う。家族も「全く込み合っていないディスニーワールドを待ち時間ゼロで楽しんだこと」を最良の思い出としているようだ。
分子標的治療との出会い
2年が経過し1999年秋に帰国した。呼吸器内科医として臨床の現場に復帰。丁度1年が経過したところでイレッサの臨床第2相試験(IDEAL-1)に参加する機会に恵まれた。FidlerラボでEGFR-TKIの実験も行ったが、ヒト肺腺がん株PC14の肺転移モデルでは全く効かなかったので、「こんな薬、効くはずない」と内心思っていた。ところが、徳島大学から3例目としてエントリーした私の患者さんが著効した。「是非このかたにはイレッサの治療を試して欲しい」との曽根教授の意向があり、私も患者さんにお勧めした。患者さんはあまり乗り気ではなかったが「先生がそこまで言うんだったら、飲んであげてもいいわよ」と同意された。治療開始1週間後、「増悪しているのではないか?」と心配で、撮影された胸部X線フィルム(当時はまだフイルムであった)を放射線部まで自分で取りに行ったが、信じられないくらい腫瘍が縮小していた。我が目を疑った。患者間違いではないかと名前を確認したが、間違っていなかった。その患者さんは、今では常識であるが(当時はもちろんわかっていなかった)EGFR-TKIが奏効する因子「女性、腺癌、非喫煙者の日本人」をすべて満たしていた。病室まで走っていって患者さんにフィルムをみせると、患者さんは涙を流しながら何度もおじぎして感謝してくれた。私は、「よかったね」と右手を差し出し握手をした。それから、その患者さんと私の間では「握手」が幸運を期待するときのおまじないになった。これが私の分子標的薬との出会いで、あまりにも印象的な出来事であった。
やっぱり研究はすばらしい
以後、ヒト肺癌細胞の多臓器転移モデルを用いて転移機構の解析や新規分子標的の探索を、臨床的にも分子標的薬のバイオマーカーの探索研究を行っている。2007年4月より金沢大学がん研究所腫瘍内科研究分野に異動する機会を与えられ、新天地でも「転移に対する分子標的治療の基礎および臨床研究」をライフワークに掲げやって行きたいと考えている。その原動力となっているのは、「転移モデルができたときの感動」であり「分子標的治療が効いて患者さんと共有した感動」だと思う。このような感動を味わうことができたのは、「大学院生の思いつき」研究を寛大な心で許容し先見的な視点に立って発展させてくれたボスや、困ったときに相談に乗り助けてくれた先輩、同僚、後輩のおかげと心から感謝している。最近、研究をする若い人が減ったと嘆かれているが、こんなにもおもしろくて、かつ感動を味わうことのできる研究をやらないのは損!研究の魅力を若い人たちに伝えて活性化するとともに、自由な発想を生かした研究ができる環境を提供できるよう努力して行きたいと思っている。そして、「転移を制する」ことで若い研究者や患者さんとより多くの感動を味わい共有できることを願っている。