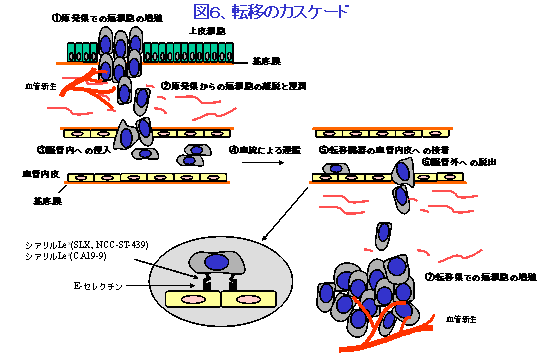がんの転移とは?
癌細胞が発生した場所(原発巣)から移動して、遠隔部位に再び腫瘍を形成することを転移という。早期診断と治療法の進歩により、癌が原発巣に限局するときの治癒率は改善してきているが、遠隔転移が形成された進行例の予後は依然として極めて不良である。したがって、癌を征圧するために転移の制御は必須であり、転移の病態を理解することは重要である。当教室では、我が国の悪性新生物死亡原因の第1位である肺癌を中心とした固形癌の転移の分子機構の理解に基づいた分子標的治療の開発を目的に研究を展開している。
転移という言葉は、1829年にフランスのRecamierが最初に使ったとされるが、1973年にFidlerらが低転移性のマウス黒色腫B16細胞から高転移性細胞の選択に成功し、それを用いた転移実験モデルを確立したことにより転移研究の基礎が築かれた。また、1986年にはLiottaにより浸潤が癌細胞と基底膜の接着、基底膜成分の分解、癌細胞の運動の3段階によって遂行されるという「Three Step Theory」が提唱された。このような癌転移の概念および実験系の確立が起爆剤となり、転移メカニズムを細胞および分子レベルで解明する研究が急速に展開されるようになった。その結果、1)癌細胞は生物学的に不均一(heterogenous)であること、2) 癌細胞は絶えざる遺伝子変異の結果転移に好都合な細胞形質を獲得し、ごく少数の転移能を有した癌細胞が転移の過程で選択され増えていくこと、3)転移の全ての過程が正常細胞と癌細胞の複雑な相互反応の上に成り立っており、接着分子、蛋白分解酵素、増殖因子、血管新生因子、ケモカインなど多くの分子が関与していることなどが明らかになってきた。また、癌の転移は決してランダムに偶然おこるわけではなく、下記に示す転移の過程を連続して全てクリアした癌細胞のみ(数百万個に1個程度と推測されている)が形成することができるため、Fidlerは転移した癌細胞はオリンピックの10種競技のチャンピオンに例えている。
II. 転移のメカニズム
転移には血行性転移、リンパ行性転移、管腔性転移(たとえば細気管支肺胞上皮癌の経気管支転移)などがあるが、そのメカニズムは基本的には似通っているため、血行性転移を例にとり概説する。血行性転移は、癌細胞の1)原発巣での増殖、2)原発巣からの癌細胞の離脱と脈管(血管やリンパ管)への浸潤、3)脈管内での移動、4)転移臓器の血管内皮への接着、5)転移臓器への浸潤、6)転移臓器内での増殖などの過程から構成されており(図6)、すべての過程が連続的に起こった結果生じる。また、全ての過程において癌細胞は免疫排除機構から逃れて生存する必要がある。