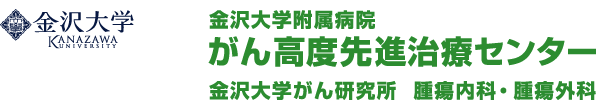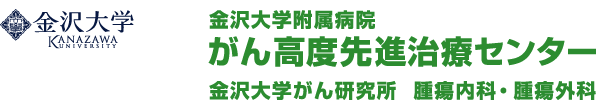EGFR-TKI耐性の克服―日本からの挑戦―
金沢大学がん進展制御研究所
腫瘍内科
矢野 聖二
EGFR-TKIの獲得耐性は臨床上重要な課題
肺がんの治療は分子標的薬の登場により劇的に変化しました。とくに上皮成長因子受容体(EGFR)に遺伝子変異のある肺がんは、約80%の症例でゲフィチニブやエルロチニブが奏効します。EGFR遺伝子変異のある肺がん症例を対象とした第III相試験において、ゲフィチニブやエルロチニブが殺細胞性抗がん薬と比較し有意に無増悪生存期間(PFS)を延長することや、このような症例群は2年半を超えて生存できることが示されました。私が医者になった20年前は、非小細胞肺がんに化学療法を行う意義があるのかどうか真剣に議論されていたような時代でしたので、隔世の感がございます。
しかし、ゲフィチニブやエルロチニブが一旦著効した症例も数年以内にほぼ例外なく再発してしまいます。これはがん細胞が薬剤に耐性を獲得するためで、この獲得耐性が臨床的に克服すべき次なる課題になっています。
日本から発信された獲得耐性因子HGF
2004年にMassachusetts General Hospital (MGH)やDana-Farber Cancer InstituteのグループによりEGFR遺伝子変異が発見されこの領域の研究が一気に注目を集めるようになりましたが、その後は獲得耐性因子の分子機構を解明する研究が主流になっています。現在臨床的に意味があることが確認された獲得耐性因子としてはEGFRのT790M二次的遺伝子変異、Met遺伝子増幅、肝細胞増殖因子(HGF)の過剰発現の3つがあります。EGFR-T790M二次的遺伝子変異は2005年にHarvard大学のグループから、Met遺伝子増幅はMGHのグループから報告されました。ゲフィチニブやエルロチニブが奏効するEGFR遺伝子変異のある肺がんは日本を含む東アジアに多いにもかかわらず、本領域の重要な発見は米国ボストンのグループからなされている状況が続いています。このような中、私たちは2008年にHGFがゲフィチニブの耐性を誘導することを明らかにし、臨床的に意味のある耐性機構であることを報告しました(図1)。
|